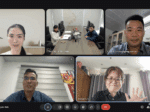コミュニケーションツール?ファミリースポーツ?〜ベトナムのピックルボール事情
- 2025/08/29
- 生活, ベトナム情報レポート
皆さんは、ピックルボールというスポーツをご存じでしょうか?1960年代にアメリカで生まれたパドル(ラケット)を使って、穴の開いたプラスチック製のボールを打ち返す、テニスとバトミントン、卓球を組み合わせたような競技で、今世界的にブームになっています。私が“ピックルボール”という言葉を初めて耳にしたのは去年のこと。日本人向けの無料情報誌で、ベトナムで流行していることを知りました。今回知り合いの紹介で、オールベトナム人のチームの練習に参加する機会を頂きました。ピックルボール愛好家のベトナム人に囲まれ、初めてプレーした日本人が感じた、ベトナムでのピックルボールブームについてお伝えします。
目次
1. ピックルボールとはどのようなスポーツか?
待ち合わせ場所に指定されたのは、ハノイ最大の湖、西湖の北側、欧米人も多く住む地域にあるピックルボール場。最近できたばかりとあって、おしゃれな外観で、きれいなロッカールームもある施設です。今、ハノイ市内には、ピックルボールブームに乗り、あちらこちらに専用コートができています。
敷地に入るとまず目についたのは駐車場です。ベンツ、BMW、ジャガーといった高級車がずらり。運転手付きの高級車に乗り、全身コーディネートされたベトナム人たちが、入れ替わりにやってくる光景を見て、ピックルボールは、ゴルフのようなハイソなスポーツなのかと思うほど。予定より1時間も早く到着してしまいましたが、カフェも併設されているので、練習風景を眺めながら、時間を過ごすには好都合でした。
平日18:00。この日、私が参加させて頂くチームのリーダー、イエンさんとメンバーが到着。集まって早々、試合形式での打ち合いが始まりました。仕事終わりに来たメンバーも合わせ、この日参加したのは、20代〜50代の男女約20名。イエンさんのご家族やその友人、ビジネスやプライベートでお付き合いがある方を中心に週3回2時間、みんなで集まり、ピックルボールを楽しんでいるそうです。学生から経営者まで、世代を超えて交流できるのもピックルボールの特徴です。
遅い時間になるにつれ、仕事帰りのサラリーマンや大学生くらいの若い人たちも多くなっていきます。曜日や時間によって、プレーをしに来る人たちの性別や年齢層は、だいぶ変わりそうです。

私もイエンさんたちに誘われ、見よう見まねでボールがパドルに当たる感触を確認しながらラリーの練習、そして2対2のミニゲームに参加しました。ボールに穴が開いている分、球速が遅く、パドルの芯に当てるのは正直それほど難しく感じませんでしたが、逆に強く叩きすぎて、ホームランになってしまうことも。「当てるだけで大丈夫よ」と言われても、人間、いざ勝負となると、やはり力が入ってしまうもの。デビュー初戦は呆気なく敗退してしまいましたが、観客よりプレーヤーの方が断然楽しいスポーツです。

2.ベトナム人がハマる理由
ベトナムでは親子3代でピックルボールを楽しむのも珍しくないですよ。そう話してくれたのは、建築家でイエンさんのご主人でもあるロンさん。テニスは似たようなスポーツですが、力を使うため、ケガもしやすい。でも、ピックルボールは余計な力は必要ないので、子どもからお年寄りまで楽しめます(この日は家族連れを見かけませんでしたが、後日日本人のピックルボール愛好家に聞いたところ、家族連れでプレーする姿をよく見るとのことでした)。特に10歳以下の子どもたちは大人と練習するものだから、上達も早いですよ。ゴルフはゴルフ場への移動にもプレーにも時間がかかるけど、ピックルボールはふらっと来てプレーをして、さっと帰ることができるところもいいです。ロンさんは仕事上のお付き合いで、ゴルフもされるとのことでしたが、ゴルフとピックルボールの良いところを、うまくビジネスで活用している印象を受けました。
以前ワシントンで寿司屋を経営されていたアキラさん(ベトナム人)。今はベトナムに戻り、投資ビジネスをされています。アメリカでのピックルボールの経験はなく、2年前にイエンさんから誘われ、始めたそうです。ピックルボールは、年齢や性別に関係なく、初心者でも気軽にできるスポーツだから良いと言います。 練習中にメンバー同士、ビジネスの話になることもあるそうですが、机に座って面と向かって話すよりもコミュニケーションもスムーズだとか。
ベトナムの日本人コミュニティでもピックルボールチームがあります。プレーの目的は、趣味や健康のため、と言った個人的理由が多いのに対し、ベトナムの人たちは、家族や仲間とのコミュニケーションツールとしての捉えているところに、日本とベトナムの違いを感じます。

3.スポーツ後の一杯は万国共通
練習後、一緒にビールを飲みに行かない?と誘われ、ロンさん・イエンさんご夫婦と練習仲間のタインさん・チさんご夫婦と一緒にビアホイ(ベトナム風ビアホール)へ。日によっては、参加者全員で食事することもあるそうです。この日のメンバーは全員同世代。この日話題になっていたのは、健康の話や数日前に亡くなったFPT(ベトナムIT業界最大手)のカリスマリーダー、ホアン・ナム・ティエンさんのことでした。若者からも絶大な人気を誇っていたという彼。FPTはベトナムに住む外国人であれば誰でも知っている大企業ですが、私自身、会長のことまではよく知りませんでした。彼の生い立ちや、なぜ若者に支持されていたか、などいろいろ教えてもらい、家に帰ってこれまでの功績などを調べるきっかけとなりました。ベトナム人同士であれば、より情報交換や新たな出会いやビジネスチャンスが生まれやすい環境と言えるでしょう。

4.アメリカからベトナムへ〜ブームになる前
イエンさんが初めてプレーしたのは、アメリカでした。始めるのにそれほど費用がかからず、誰もが楽しめるスポーツであることを実感し、友人らを集めてベトナムでチームを発足したのは2年前。ベトナムでピックルボールがブレイクする前のことでした。専用のパドルやボールはベトナムで販売されておらず、アメリカで購入してベトナムに持ち帰り、テニスコートで練習をしていたそうです。
イエンさんのようにアメリカに行ったことがある方や、留学や仕事でアメリカに住むベトナム人、移住したベトナム系アメリカ人たちが、祖国に持ち込み、次第に広がり、昨今のブームに繋がったと思われます。
5.ピックルボールのお値段事情
ベトナムのピックルボールブームの要因の1つに、手軽さがあります。
パドル
初心者向けの低価格モデルからプロユースのものまで、町のスポーツ用品店やネット通販で手に入ります。安いものでは50万VND(約 3,000円)で購入でき、4〜5万円もする軽くて高性能なものも販売されています。テニスやバトミントンのようなガットの張り替えがないため、ランニングコストはかかりませんが、使用し続けているうちに少しずつ性能が落ちるため、1〜2年程度で新しいものに交換するのが一般的で、複数本を使い分けている方もいるようです。
これまでは海外からの輸入品に頼っていましたが、最近ではベトナムで制作したパドルを販売するメーカーも出てきたようです。スポーツ用品の輸入には7.5%の一般関税(条件によって異なる)とVAT(付加価値税)8%がかかり、それが商品の値段に反映される訳ですから、海外に行く機会が多いベトナム人にとっては、国内で購入するよりも、海外で購入する方が安いと感じるでしょう。

コート使用料
今回訪問したピックルボール場は、ハノイ中心部から車で15分ほどの場所にあります。朝6:00〜深夜24:00まで営業しており、1コート1時間で、16万〜37万VND(約1,000〜2,100円/時間帯によって異なる)。1グループ最低6名で来ているので、混雑する時間帯でも、1人1時間400円弱、ランチ1食分程度でプレーできると考えると、誰でも気軽にはじめやすいスポーツだと言えます。
6.ブームがブームで終わらないために
2025年3月14日付のTuoi Treのウェブニュースは、ベトナムのピックルボールの競技人口(“にわかプレーヤー”を除く)は3万人で、昨年に比べ2倍に増えた、と報じています。また今年からは、全国レベルの大会も開催されるようになり、ベトナム全土で毎週大小合わせて数十の大会が行われている一方、人気スポーツとして急成長を遂げているにも関わらず、まだ「ピックルボール協会」のような組織はなく、ようやく設立に向けて動きはじめたところ。急激な競技人口に対し、体制が追い付いていないのが現状のようです。
ベトナムのピックルボールの将来はいかに?以下、ベトナム在住の私の私見です。
まず本格的に協会が立ち上がれば、さらに広範囲へ普及が加速し、審判の育成も行われ、ルールや判定方法を統一することで、試合の公平性が期待できます。また今後、国産の競技用品ブランドが確立すれば、良い品質の商品がリーズナブルな値段で購入でき、競技人口増加の後押しになるでしょう。更にファッショングッズなども同時展開することで、オシャレにスポーツを楽しみたい女性たちからの支持を得やすくなります。
懸念材料を挙げるとすれば、プレー代の高騰でしょうか。今回参加させて頂いたチームメンバーの方から、コートが増えたにも関わらず、コート使用料はこの2年で1.2倍ほど上がったと伺いました。ベトナムでのゴルフのプレー代は高くて有名ですが、このように一部のお金持ちしかできないスポーツのイメージが定着すると、普及の妨げになります。
手軽にでき、みんなで楽しめるスポーツとして広まったピックルボール。競技者、メーカー、販売店それぞれが原点を忘れずにいることができれば、ブームではなく、継続的に競技人口は増え、市場は自ずと広がっていくのではないでしょうか。
文=土佐谷由美
さらに詳細な情報を知りたい場合は
下記よりお問い合わせください。