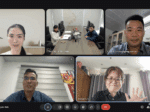町を彩るベトナム秋の風物詩〜中秋節
- 2025/09/25
- ベトナム観光旅行記

10月6日は、中秋節。私たち日本人には「十五夜」「お月見」という呼び名の方が、馴染みがありますが、毎年旧暦8月15日に行われる中国発祥の東アジアに伝わる伝統的なイベントです。日本ではススキの飾り、お月見団子で静かに月を愛でるというイメージがありますが、ここベトナムでは、色とりどりの飾りを目にしたり、ショッピングモールや高層アパート付近に特設の月餅店が並ぶようになると、「今年もこの時期がやってきた!」と思うほど、華やかな行事です。
1.町中で感じる中秋節
① ⽉餅
⽇本のお⽉⾒に⽋かせないものは⽉⾒団⼦、ベトナムの中秋節には⽋かせないお菓⼦と⾔えば、月餅でしょう。この時期は、スーパーや菓⼦店だけでなく、⼤⼿カフェチェーンのスターバックスなどでもオリジナルの⽉餅が販売され、また⼈が集まる場所には必ずと⾔っていいほど⽉餅屋台があり、町中で販売合戦が繰り広げられます。
⽉餅の丸い形は団結の印で、会社や友達同⼠、取引先などに贈り合う習慣があります。私も会社勤めをしていた頃は、毎年会社から⽉餅を頂いていました。中秋節のだいぶ前に配るので、ベトナムに来た当初、ベトナム⼈の同僚に「まだ中秋節じゃないけど」と尋ねたことがあります。頂いた⽉餅を、しばらく家で飾ってから⾷べるのが⼀般的であるため、当⽇ではなく、早めに贈るのがベトナム流だとか。確かに結婚式の引き出物が⼊っているようなデザイン性のある⾼級パッケージに⼊れたまま部屋に飾ると、なんとも縁起が良さそうです。
伝統的な⽉餅は、Bánh nướng(バインヌオン/焼き⽉餅)と Bánh dẻo(バインゼオ/ ⽩いお餅の⽉餅)です。バインヌオンは焼いて⽪が茶⾊になったもので、中⾝はナッツやドライフルーツなど様々ですが、満⽉を模した塩漬け卵⻩が特徴的です。 ⼀⽅、バインゼオは表⾯が真っ⽩で柔らかく、中には緑⾖や蓮の実餡が⼊っているものが⼀般的です。 最近では、抹茶味やコーヒー味、チーズ味などの変わり種や、⾷べきりサイズの⼩ぶりの⽉餅が⼈気だそうです。

旧市街内、ハンザ市場前に設けられた⽉餅屋台。

最近は伝統的なものだけでなく、若者向けに新しい味の⽉餅も増えてきた。
② 飾り
ハノイで中秋節のお祭り気分を味わいたいのであれば、 迷わず旧市街のハンマー通りをおすすめします。この通りは、元々冠婚葬祭や年中⾏事に使われる飾りを扱っていますが、中秋節前のこの時期は、テト(旧正⽉) 前と並んで、1 年で最も華やか。⾊とりどりのセロハン製のランタンや張⼦のお⾯、⽶粉でできたミニチュアなど⼿作りの品が、所狭しと並んでいます。昔、ランタンにはろうそくを灯していたそうですが、今は⾖電球に取って代わってしまうなど、時代と共に仕様が少しずつ変わってはいるものの、初めて⾒る⼈でもどこか懐かしく感じられるものが多いので、⾒ているだけでも楽しい気分になるのではないでしょうか。
夜のハンマー通りは、セロハン製のランタンに電気が灯され、昼間より⼀層、華やいで⾒えます。時間がある⽅は昼と夜、時間を変えて訪れてみるのもよいでしょう。

夜のハンマー通りは昼間より幻想的に。

⽶粉で作られたミニチュア。カラフルな飾りや⼩物は⾒ているだけでも楽しい。
③ 獅⼦舞
悪霊を追い払い、⼦どもたちに幸運をもたらすための踊りも中秋節には⽋かせません。⽇本語では 「獅⼦舞」と訳されていますが、ベトナム語で múa lân(ムアラン)や múa lân sư rồng(ムアランスーゾン)と呼ばれ、ムアランの“ラン”は、吉祥の象徴とされる“麟”(麒麟のメス/ベトナム⽂化では麒麟のオスは存在しない)のことなので、「麒麟舞」の呼び⽅の⽅が、より正確かもしれません。実際の舞には、麒麟の他、獅⼦や⿓を加えた三聖獣が登場します。⽇本で獅⼦舞は、お正⽉くらいにしか⾒かけることはありませんが、ベトナムでは会社の設⽴や結婚式などの⾏事でも披露されるので、⽇本に⽐べて⽬にする機会は多いです。
1つの獅⼦(麒麟)は 2 名で演じられるため、アクロバティックな動きもあり、⼦どもたちだけでなく、⼤⼈でも楽しめます。決められたステージで踊られるというよりは、路上や広場、お店の前などで踊られます。私も毎年、ホアンキエム湖付近の路上で⾏われているものを観に⾏きますが、太⿎の⾳に合わせ⼤きく踊る姿は、側で観ていてとても迫⼒があります。また私が住んでいる地域では、道路を歩きながら、獅⼦舞を披露しています。⼦どもたちが楽しそうに獅⼦舞の後について⾏く姿は、まるで⽇本の秋祭りのようです。
2.クオイの伝説〜ベトナム中秋節の起源
ベトナム語で中秋節は、“Tết Trung Thu(テト チュン トゥ)と⾔います。その昔、⽊こりのクオイの妻が神聖なガジュマルの⽊に尿をしてしまい、その⽊の枝に座った途端、⽊は成⻑を始め、クオイ夫妻は⽉まで⾶んでいってしまった、との有名な伝説があります。クオイとその妻に地上へ帰る道を教えるため、中秋節の間、⼦どもたちがランタンを灯して⾏列を作っていたのが、そのまま⾏事として定着したようです。現在ハノイでは、⼦どもたちがランタンを持って、町を練り歩く光景を⾒ることはそう多くはありませんが、40 代の地⽅出⾝の知⼈は、幼い頃、友だちと⼀緒にランタンを持って、近所の家を周り、お菓⼦をもらうのが楽しみだったと話してくれました。
また⽉と⾔えば、その模様から、⽇本ではウサギが住んでいる、という⾔い伝えがあります。 私も幼い頃、お⽉様を⾒ながら、⺟親から 「⽉にはウサギが住んでいて、ぺったんぺったん餅をついているんだよ」 教えてもらいました。ベトナムでは⽉の模様は、「ガジュマルの下におじさんが座っている」姿だそう。ウサギとおじさんでは、だいぶ印象が違いますが、これも所変われば、ですね。

星型の飾り“Đen ông sao ” (デンオンサオ)。 新しいスタートへの希望を意味する中秋節の定番飾り。

セロハンでできたランタン。動物や船、蝶々など様々なデザインとサイズがあり、どれを買おうか迷ってしまう。
3.中秋節は、第2の⼦どもの⽇
ベトナムの中秋節の特徴として、⼦どものためのお祭りとしての要素が強いことが挙げられます。ベトナムでは、6⽉1⽇を⼦どもの⽇として制定していますが、中秋節は「第2の⼦どもの⽇」とも⾔われているほど、⼦どもたちにとって⼤切な⾏事です。ただし、中秋節が⼦どものお祭りとして定着したのは、ごく最近になってからのこと。 ホー・チ・ミン国家主席が毎年、中秋節に合わせて全国の⼦どもたちに⼿紙を送っていたことが、徐々に⼦どものための⽇と変化したと⾔われています。
実際⼦どもがいる家庭では、どのように中秋節を過ごすのでしょう。ベトナム⼈の旦那様と 3 ⼈のお⼦さん、義理のご両親と⼀緒にお住まいの⽇本⼈の Mayu さんに、話を伺いました。
中秋節当⽇(⼟⽇にあたる場合は、その前)には、幼稚園や⼩学校でお祝いします。学校によっては、家から中秋節の飾りを持って来てほしいと連絡があり、当⽇果物で作った飾りを持って⾏き、教室に飾ります。また園児、⽣徒、先⽣みんなでアオザイを着て登園・登校し、お遊戯会などのイベントが⾏われ、給⾷も中秋節⽤の特別メニューが提供されます。⽗⺟会(⽇本でいう PTA にあたるもの)からも⼦どもたちに、お菓⼦など⾷べ物のプレゼントがあります。幼稚園や学校によっては、近所の⼤⼈たちがやってきて、獅⼦舞を披露してくれるそうです。住んでいる地区(⽇本でいう町会にあたるもの)からもお菓⼦や⽜乳などが配られたり、近所の⼤⼈から、ちょうちんやセロハン製の飾りなどを頂いてくることもあります。私の家では、中秋節だからといって特別なことをする訳ではありませんが、家族で⼀緒に時間を過ごします。6⽉1⽇のベトナム⼦どもの⽇は、⼩学校がすでに夏休みに⼊っていることもあり、第2の⼦どもの⽇である中秋節の⽅が、盛⼤にお祝いしている気がします。親よりもむしろ周りの⼤⼈たちが⼦どもたちにプレゼントを贈ったり、⼦どもたちが喜ぶようなことを企画してくれます。そういう光景を⾒ると、ベトナムは⼦どもを⼤切にする国だな、と改めて感じます。

中秋節に合わせ、幼稚園や⼩学校ではお祝いイベントが開かれる。© Mayu Yamamoto

各家庭から持ち寄られた中秋節の飾り。左の⽝は、ザボン(グレープフルーツ)で作られている 。 © Mayu Yamamoto

近所の⼦どもたちが集まって、⼀緒にお祝い。© Mayu Yamamoto
年中⾏事を通して学ぶ現地の⾵習は、その国の⽂化を知る上でとても興味深く、有意義なことです。⾝近にベトナム⼈のお⼦さんがいらっしゃるようでしたら、お菓⼦などプレゼントしてみてはいかがでしょうか?
文=土佐谷 由美
さらに詳細な情報を知りたい場合は
下記よりお問い合わせください。