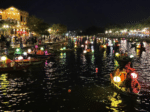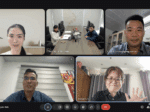建築はみて、ふれることのできる歴史〜ハノイ近代建築
- 2024/02/05
- ベトナム観光旅行記

「建築はみて、ふれることのできる歴史」わたしの友人の建築家はそういいます。ハノイの古い欧風建築の多くは、ベトナムがフランス植民地時代、19世紀から20世紀初頭に建てられたものです。ベトナムがフランスの植民地支配を受けた時期のあったことを、これらの建築物は示しています。
ベトナム戦争当時、米軍による空からの爆撃を受けて破壊された建物もあります。しかしそれを修復し、いまだに自らの国の歴史の「生き証人」として、戦争の爪痕を今に伝える建物もあります。
ベトナムにおける近代建築の数々を愛でながら、ベトナムの歴史に思いをはせる旅はいかがでしょうか?
今回、4つのハノイの近代建築をご紹介いたします。
ハノイ大教会

ハノイ市の中心にあるホアンキエム湖。週末ともなれば、周囲の道路は車両通行禁止なって、ハノイの若者や家族連れで賑わいます。その湖から教会通りへ数100メートル歩くと、その突き当たりに2つの鐘楼のあるゴシック建築のハノイ大教会があります。
ベトナムはアジア諸国の中でも5番目にカトリック信者の多い国で、信徒は700万人以上いるとされています。16世紀に欧州の宣教師により布教が開始され、日本におけるキリスト教迫害を受けて、日本人宣教師も数多くベトナムにわたり布教しました。
ハノイ大教会は聖ヨセフ大聖堂という正式名称があります。ハノイ大司教区、32万信徒を抱える教会です。
教会の建物は1882年に建設が開始され、1886年12月の聖誕祭に完成披露されました。全長55m、幅33m、屋根の高さ17m、鐘楼の高さは31mとこぶりではありますが、中世ゴシック建築が見直された19世紀らしいゴシックリバイバル建築で、正面の大きなバラ窓が特徴的です。
建築資材としては石ではなく、ベトナムで調達が可能な焼成レンガと石灰モルタル、カートン紙が使用されました。正面に据えられた時計と大小5つの鐘は欧州から輸入されました。
建築予算は20万フラン、のべ3千名が動員されて建設されました。資金の一部は宝くじを発行して賄われました。宝くじの賞金は現金ではなく、ベトナムの美術工芸品だったそうです。
1年をかけて、外壁は4層の塗り替えが行われ、一時は灰色ののっぺりとした色をしていましたが、今は塗り替え前と同様に古くみせるための塗装が施され、百数十年の歴史を感じさせるものになっています。
昨年2023年にはベトナム国家主席がバチカンを訪問し、年末には両国にそれぞれの正式な代表事務所が開設され、ローマ・カトリックとベトナムとの関係正常化が進んでいます。2024年にはローマ教皇のベトナム訪問が実現するかも知れません。
オペラハウス

19世紀、フランスは奴隷制度は「非人道的」だと反対する一方、未開に文明をもたらす植民地は「人道的」だとして、アフリカやアジアでの植民地化しました。そして自らの植民地に監獄とオペラハウスを建設しました。
1899年にフランス公使が総督に対してオペラハウス建設を建議し承認され、1901年から10年の歳月をかけて建設されたのが、ハノイのオペラハウスです。
総工費20万フラン、二人のフランス人建築家の設計による新古典主義的な建築物です。パリのオペラ座・ガルニエ宮を模したと伝えられますが、横幅125mのガルニエ宮に比べて、ハノイのオペラハウスは30mと約4分の1、規模もさることながら、数々の彫刻で装飾されたパリのそれと比較して簡素化されたイメージは拭えません。
当時の客席は870席。主に在インドシナのフランス人とベトナム人の富裕層によって使用されました。
1941年12月、まさに米英との戦争が開始される前後に、日本・仏領インドシナの文化交流の一環として、日劇ダンシングチームによる演奏会もこのオペラハウスで催されています。当時、英語は敵性語であるとされ、チームの名称は東宝(東京宝塚)舞踏隊と呼ばれていました。
1945年8月革命では、オペラハウス前の広場がホーチミンが指導する革命組織、ベトミン(ベトナム独立同盟会)の集会が行われ、ベトナム初の国会もここで開催されました。1995年から2年間にわたり改装工事が行われ、往時の装いを取り戻したオペラハウス。日本人指揮者・本名徹次氏を音楽監督に迎えたベトナム国立交響楽団をはじめ、ベトナム国内外の音楽家や劇団が公演を行っています。
大理石が敷かれた床、壮麗な天井画。天井桟敷で優雅に音楽やオペラを楽しむことが、このハノイでできます。2023年には日越外交樹立50周年を記念して、ご朱印船時代の日越恋物語・オペラ「アニオー姫」が上演されました。
ハノイ駅

19世紀、陸上における大量輸送機関として、重要な位置を占めたのは蒸気機関車によって車両を牽引する鉄道でした。英国で鉄道が発明されると、一気に欧州の列強諸国は自国に鉄道を敷設するばかりか、アジアの植民地にも鉄道網を築きました。
唯一、日本は外国管轄方式を断り、自国管轄方式で鉄道を敷設しました。1872年、明治5年には英国の技術協力を得て、新橋〜横浜間に営業鉄道を開通させました。
フランス植民地であったインドシナでは、1881年にサイゴン(元ホーチミン市)〜チョロン間を路面電車が、1885年にはサイゴン〜ミト間にメーターゲージ(1000m幅軌道)の営業鉄道が開始されました。
19世紀の末、インドシナ総督に任命されたポール・ドゥメールはインドシナにおける鉄道網を構想しました。主にはハノイからサイゴンまで、ハイフォンからハノイを経由して中国・雲南までと、ベトナムとラオス、ベトナムとカンボジアとを結ぶ路線でした。
優先的に建設されたのは、ハイフォンからハノイ、ハノイからラオカイを経て雲南・昆明に向かう鉄道でした。
1902年にはハノイ駅、当時の名称はハノイセンター駅という名称でしたが、一派にはハンコー(草通り)駅と呼ばれて親しまれました。この地域が昔、馬や牛の飼料となる草を売る場所だったからです。
1954年からは北緯17度線を境界に鉄道も南北に分断され、統一鉄道が走行するようになったのはベトナム南北が統一された1976年からです。
1972年には米軍によるハノイへの空爆で、ハノイ駅の駅舎中央部分は大きく破壊されます。その後、駅舎の両翼とはそぐわない現代的な駅舎が中央部分に造られます。これが現在ハノイ駅が特異な形状をしていることの由縁です。
雲南から中越国境の街・河口までは標準軌道の高速鉄道が中国によって敷設されました。そこから延伸してハノイ、ハイフォンまで標準軌の鉄道が走行する予定です。
ロンビエン橋

ハノイの中心部の東側を流れる大河、紅河。雨季ともなると、上流から流れてくる赤土のゆえか、紅色の河の流れをみることができます。
この河の両岸にかかる橋は現在、5つあります。その中でもっとも古くからあるのがロンビエン橋です。1902年に竣工した鉄道橋です。
この橋はハノイからハイフォン、そしてハノイからラオカイを経て中国・昆明へと向かう鉄道線路のための橋として造られた鉄橋です。全長1681m、20の橋台をもち、19のトラス構造の主構をもっていました。竣工当時は植民地の鉄道網を計画したフランス人総督、ポール・ドゥメールの名前からドゥメール橋と名付けられました。革命後、ロンビエン橋と名前が改められました。
1887年、フランスの建設会社6社がこの橋の入札に参加しました。入札の結果、選ばれたのはDaydé & Pillé社でした。かつてこの橋はパリのエッフェル塔で有名な設計者グスタフ・エッフェルの設計によるものとと伝えられていました。
しかしベトナム国立公文書館で保管されていた文書を確認したところ、設計図には、建設会社の技師、総督ドゥメールの署名があるだけで、エッフェルの署名はありませんでした。ロンビエン橋の設計にエッフェルが関わっていたというのは誤りだとわかりました。
1966年から67年にかけて米軍による北爆が激しかったころ、首都ハノイとハイフォン港を結ぶ物流の要となっていたロンビエン橋は爆撃の対象となり、なんども攻撃を受けて、橋が落とされました。破壊のたびに橋は修復され、今も現役の鉄道橋として存在しています。ただ、鉄製トラスの主構は失われて、別の素材による橋になっている部分があることが、この橋に対する空爆の激しさを物語っています。
橋の掛け替えが取り沙汰されるために保存運動がおきました。現在、フランス政府の援助も受け、橋を保存する方向で検討されていると報じられています。
文=新妻東一
さらに詳細な情報を知りたい場合は
下記よりお問い合わせください。